今日のお題:伊達聖伸先生編著『ヨーロッパの世俗と宗教:近世から現代まで』(勁草書房、2020年10月)をご恵贈賜る。
伊達聖伸先生編著『ヨーロッパの世俗と宗教:近世から現代まで』(勁草書房、2020年10月)をご恵贈賜る。まことにありがとうございます。
k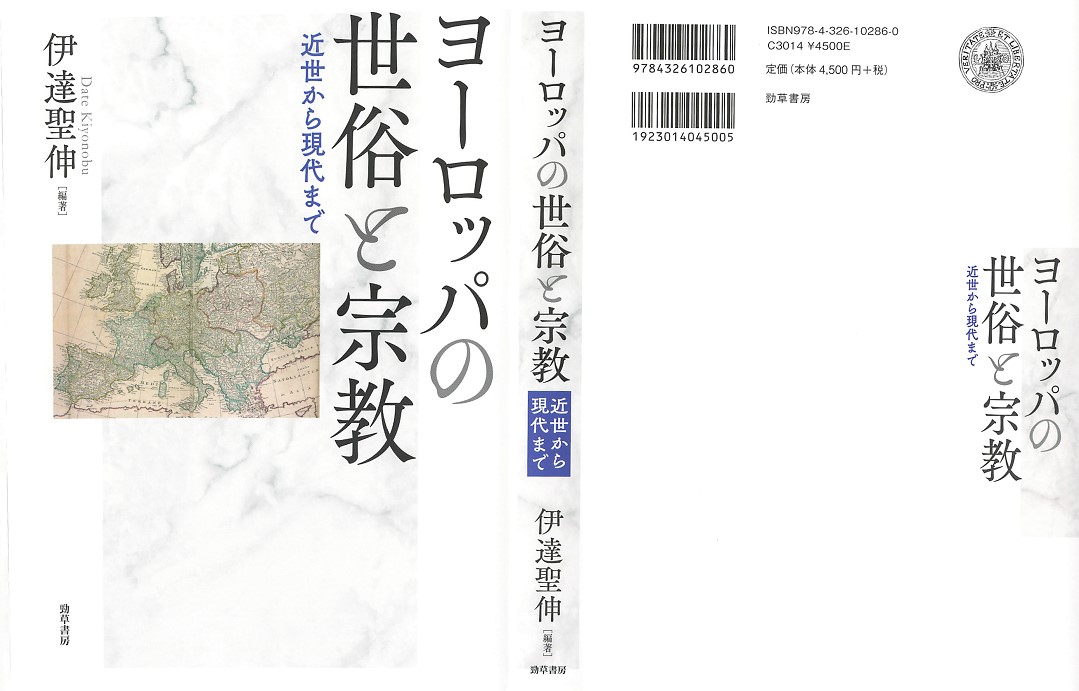
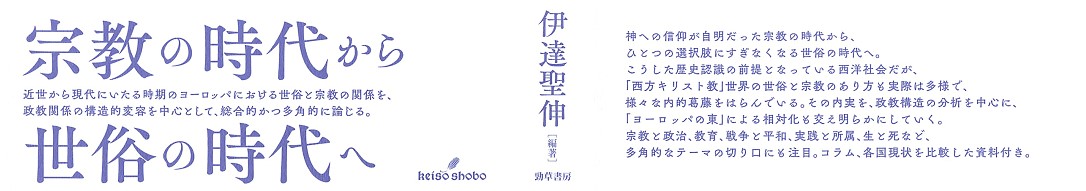
ヨーロッパの世俗と宗教 - 株式会社 勁草書房
https://www.keisoshobo.co.jp/book/b535778.html
付札が「執筆者一同」のため、どなたから頂戴したのかが分かりませんが、いずれ己れの不義理の故かと痛み入る次第でございます。
さて本書の特筆すべき所は、やはり第一部の総論であろうかと。これほどまでに「ヨーロッパ」における「宗教」を広範かつ丁寧に叙述するのは、かなり難儀であったであろうと思う次第でございます。
ここで大事なのは、「キリスト教史」ではなく、「宗教史」だということですね。「宗教」というモノがいかに認識され――正確に言えば「宗教」と認識される対象がいかに確立したのか――、そしてそれがいかに変容していったのかというのを非常に多面的に描いているわけです。
で、これを一人の人間が出来ようはずもないので、合作となっているのですが、その分担は目次からは分かりませんので、序論を参考に復元してみますとこんな感じで近世から現代までの各地域が描かれることになっています。間違ってましたら申し訳ございません。とくに南欧の辺りは推測が入っております。しかし、西・独・英・仏を一気に描ききる伊達さんの筆力というのは、とんでもないものだなぁと思う所ではございます。
1-4 西・独・英・仏:スケッチ・伊達聖伸、加筆訂正・小川公代、木村護郎クリストフ
5 南欧・伊:江川純一、葡:オリオン・クラウタウ
6 東中欧・波:加藤久子
7 南東欧・バルカン地域:立田由紀恵
8 露:井上まどか
「日本の〈ヨーロッパ〉は狭すぎる!」(例の○天モバイル風にお読みください)
というのは、夙に思うところでございまして、このくらい揃って初めて「ヨーロッパ」という冠が許されるというもの。
むしろ江戸期のヨーロッパ叙述は、ローマ帝国から出発しているので、むしろ広いわけです。その辺りの日本人のヨーロッパ認識の変容というのもまた面白いところではございます。
おっと脱線。
で、もう一つ、本書のとても大事な、絶対に欠いてはいけない箇所は、「資料編」でございます。
資料編
1.各国別宗教人口比と宗教人口比将来予想 →2020年現在と2050年(!)予想
2.礼拝出席率
3.政教関係
4.公立校における宗教教育
5.ヴェール禁止とニカブ・ブルカ禁止
6.人工妊娠中絶と同性婚の合法化
7.平均寿命と安楽死・医師幇助自殺
おそらく地域研究を専門になさっている方々には、各々の国や地域の宗教状況というのは常識の範囲内なのでしょうが、最新の情報をこれをヨーロッパというカテゴリで統合し、再配列して、さらに日本語にして下さったことには感謝しかございません。これであと十年は戦えます。いや、2050年予想を考えると30年でしょうか。
ということで、ヨーロッパ自体に関心があまりない方でも、宗教を考えたい方であれば、まずはポチッとして戴きたい。
ヨーロッパの世俗と宗教: 近世から現代まで | 聖伸, 伊達 |本 | 通販 | Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/4326102861
【目次】
序論 本書の目的・特色・構成(伊達聖伸)
第Ⅰ部 総論 世俗の時代のヨーロッパにおける政教関係の構造と変容
(伊達聖伸、小川公代、木村護郎クリストフ、内村俊太、江川純一、オリオン・クラウタウ、加藤久子、立田由紀恵、井上まどか)
はじめに
第1章 近世─宗教改革から領域主権国家の確立と王権の強化まで(一六世紀~一八世紀)
一 スペイン─レコンキスタとカトリック的な王国の形成
二 ドイツ─宗教改革から領邦教会制へ
三 イギリス─国教会の成立から二つの革命へ
四 フランス─宗教戦争から絶対王政へ
五 南欧─教会国家再編のイタリア、王権強化のポルトガル
六 東中欧─宗教改革の「先行性」と帝国的な「宗派化」のもとの寛容
七 南東欧バルカン地域─オスマン帝国統治下の寛容と「イスラーム化
八 ロシア─正教における帝権と教権、そして宗派化と帝国的な「寛容
第2章 近代─世俗的世界観の覇権の時代(一九世紀~二〇世紀前半)
一 フランス─「二つのフランスの争い」とライシテの確立
二 スペイン─「二つのスペインの争い」か、カトリックの優位か
三 イギリス─国教徒と非国教徒の作り出すダイナミズム
四 ドイツ─政教分離の論理とプロテスタント的なナショナル・アイデンティティ
五 南欧─「二つのイタリアの争い」、「二つのポルトガルの争い」
六 東中欧─帝国(のはざま)の政治的・宗教的アイデンティティ
七 南東欧バルカン地域─反西欧的な宗教的ナショナリズム
八 ロシア─宗教的ロシアに対する二つの評価とソヴィエト体制下の政教分離
第3章 現代─宗教的なものの回帰と再構成(二〇世紀後半以降)
一 スペイン─イスラームに寛容なカトリック的ライシテの国?
二 ドイツ─「キリスト教優遇型」の存続か変化か
三 イギリス─多様性の承認とブリティッシュネスの共有
四 フランス─ライシテの試練
五 南欧─カトリック優位の「宗教的多元主義」
六 東中欧─社会主義体制下の無神論から冷戦後のカトリック復興へ
七 南東欧バルカン地域─宗教とナショナリズムの結合と再活性化
八 ロシア─自由と管理の独特の編成
おわりに
第Ⅱ部 各論 世俗的ヨーロッパにおける宗教的なものの輪郭
〈政教関係の自明性を揺さぶる〉
第1章 一六、一七世紀スペインにおける政教関係─複合君主政と国家教会化(内村俊太)
はじめに
一 地域国家の政体
二 教会制度と国王教会保護権
三 複合君主政の下での国家教会化
おわりに
コラム:ポルトガルのカトリック教会と「独立」問題(西脇靖洋)
第2章 ポルトガルにおける権威主義体制の民主化とカトリック教会─リスボン総大司教アントニオ・リベイロの役割に注目して(西脇靖洋)
はじめに
一 権威主義体制の崩壊とカトリック教会
二 暫定期におけるカトリック教会
三 民主主義体制への移行とカトリック教会
おわりに
コラム:歴史を見る際の「補助線」としての理論的枠組み(内村俊太)
〈教育のなかの宗教を問う〉
第3章 ヨーロッパの公教育制度におけるイスラーム教育導入のプロセスと論点(見原礼子)
はじめに
一 ヨーロッパの公的教育機関における宗教
二 イスラーム教育導入のプロセスと論点
おわりに─ムスリムにとってのイスラーム教育の意味
コラム:世俗化社会における宗教教育と共生(増田一夫)
第4章 国家の世俗性のゆくえ─ロシアの宗教教育を事例として(井上まどか)
はじめに─ロシアにおける宗教復興と宗教教育
一 一九九〇年代の方向転換─宗教文化教育への道のり
二 「世俗性」原則をめぐって
おわりに
コラム:多民族国家における宗教教育(見原礼子)
〈宗教が対立と和解に関与するとき〉
第5章 冷戦下での西ドイツ・ポーランドの和解に宗教はどう関与したのか(木村護郎クリストフ・加藤久子)
はじめに
一 ドイツの側から─プロテスタント教会の『覚書』による世論の喚起と代替言説の提示
二 ポーランドの側から─カトリック司教団「声明」が残した葛藤と新たな自己理解
おわりに
コラム:「オトナになろう」と背中を押してくれる存在(立田由紀恵)
第6章 スレブレニツァのモスクと教会─内戦後のボスニアにおける宗教と社会(立田由紀恵)
はじめに─ボスニアにおける宗教、ナショナリズム、戦争
一 スレブレニツァとは─歴史と現状
二 スレブレニツァにおける宗教
三 スレブレニツァの宗教指導者による融和への道の模索
おわりに
コラム:スレブレニツァはヨーロッパの試験?(加藤久子)
〈宗教を信仰・実践・所属に分節化する〉
第7章 一九世紀イギリス文学の「世俗化」─エミリー・ブロンテの『嵐が丘』とスピリチュアリティ(小川公代)
はじめに
一 〈教会〉から離れても〈スピリチュアリティ〉はある
二 メソディズムの感受性文化─国教会と非国教会のあいだ
三 物質/身体と霊の融合
おわりに
コラム:霊性の彷徨はどこに向かうのか(木村護郎クリストフ)
第8章 聖母巡礼地における所属と実践─メジュゴリエの事例(岡本亮輔)
はじめに─「危険」な聖母出現
一 メジュゴリエを取り巻く三つの対立
二 ゴスパの政治的インパクト
三 所属から実践へ
おわりに
コラム:ヨーロッパ的現象としてのゴスパ出現(諸岡了介)
〈多様な生と(不)死の時代に〉
第9章 現代イギリスにおける宗教的多様性とホスピス(諸岡了介)
はじめに
一 問題の背景
二 宗教的多様性に応じた取り組み
三 チャプレン職の供給
四 ホスピスの文化的基盤
おわりに─将来の社会的課題
コラム:ホスピスケア、イギリスとロシアの共通点(井上まどか)
第10章 トランスヒューマニズムと「人新世」─科学技術時代の「信」のゆくえ(増田一夫)
はじめに─自己の身体とその境界
一 ディスラプションの時代
二 トランスヒューマニズムの宗教性
三 テクノロジーの形而上学vs自然の宗教
おわりに─超越としての人間
コラム:「トランスヒューマニズム」の系譜をロマン主義運動まで辿る(小川公代)
資料編
1.各国別宗教人口比と宗教人口比将来予想
2.礼拝出席率
3.政教関係
4.公立校における宗教教育
5.ヴェール禁止とニカブ・ブルカ禁止
6.人工妊娠中絶と同性婚の合法化
7.平均寿命と安楽死・医師幇助自殺
k
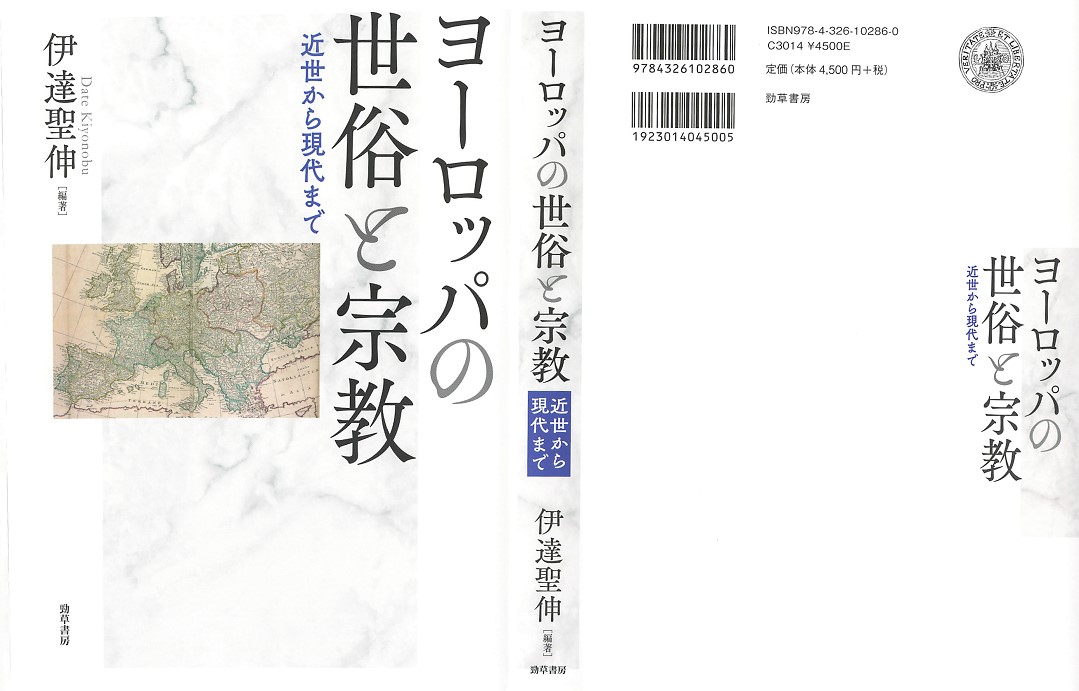
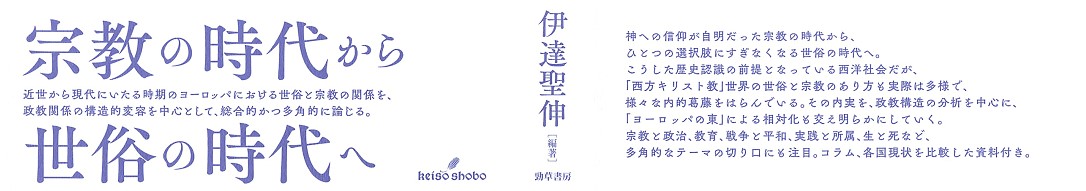
ヨーロッパの世俗と宗教 - 株式会社 勁草書房
https://www.keisoshobo.co.jp/book/b535778.html
付札が「執筆者一同」のため、どなたから頂戴したのかが分かりませんが、いずれ己れの不義理の故かと痛み入る次第でございます。
さて本書の特筆すべき所は、やはり第一部の総論であろうかと。これほどまでに「ヨーロッパ」における「宗教」を広範かつ丁寧に叙述するのは、かなり難儀であったであろうと思う次第でございます。
ここで大事なのは、「キリスト教史」ではなく、「宗教史」だということですね。「宗教」というモノがいかに認識され――正確に言えば「宗教」と認識される対象がいかに確立したのか――、そしてそれがいかに変容していったのかというのを非常に多面的に描いているわけです。
で、これを一人の人間が出来ようはずもないので、合作となっているのですが、その分担は目次からは分かりませんので、序論を参考に復元してみますとこんな感じで近世から現代までの各地域が描かれることになっています。間違ってましたら申し訳ございません。とくに南欧の辺りは推測が入っております。しかし、西・独・英・仏を一気に描ききる伊達さんの筆力というのは、とんでもないものだなぁと思う所ではございます。
1-4 西・独・英・仏:スケッチ・伊達聖伸、加筆訂正・小川公代、木村護郎クリストフ
5 南欧・伊:江川純一、葡:オリオン・クラウタウ
6 東中欧・波:加藤久子
7 南東欧・バルカン地域:立田由紀恵
8 露:井上まどか
「日本の〈ヨーロッパ〉は狭すぎる!」(例の○天モバイル風にお読みください)
というのは、夙に思うところでございまして、このくらい揃って初めて「ヨーロッパ」という冠が許されるというもの。
むしろ江戸期のヨーロッパ叙述は、ローマ帝国から出発しているので、むしろ広いわけです。その辺りの日本人のヨーロッパ認識の変容というのもまた面白いところではございます。
おっと脱線。
で、もう一つ、本書のとても大事な、絶対に欠いてはいけない箇所は、「資料編」でございます。
資料編
1.各国別宗教人口比と宗教人口比将来予想 →2020年現在と2050年(!)予想
2.礼拝出席率
3.政教関係
4.公立校における宗教教育
5.ヴェール禁止とニカブ・ブルカ禁止
6.人工妊娠中絶と同性婚の合法化
7.平均寿命と安楽死・医師幇助自殺
おそらく地域研究を専門になさっている方々には、各々の国や地域の宗教状況というのは常識の範囲内なのでしょうが、最新の情報をこれをヨーロッパというカテゴリで統合し、再配列して、さらに日本語にして下さったことには感謝しかございません。これであと十年は戦えます。いや、2050年予想を考えると30年でしょうか。
ということで、ヨーロッパ自体に関心があまりない方でも、宗教を考えたい方であれば、まずはポチッとして戴きたい。
ヨーロッパの世俗と宗教: 近世から現代まで | 聖伸, 伊達 |本 | 通販 | Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/4326102861
【目次】
序論 本書の目的・特色・構成(伊達聖伸)
第Ⅰ部 総論 世俗の時代のヨーロッパにおける政教関係の構造と変容
(伊達聖伸、小川公代、木村護郎クリストフ、内村俊太、江川純一、オリオン・クラウタウ、加藤久子、立田由紀恵、井上まどか)
はじめに
第1章 近世─宗教改革から領域主権国家の確立と王権の強化まで(一六世紀~一八世紀)
一 スペイン─レコンキスタとカトリック的な王国の形成
二 ドイツ─宗教改革から領邦教会制へ
三 イギリス─国教会の成立から二つの革命へ
四 フランス─宗教戦争から絶対王政へ
五 南欧─教会国家再編のイタリア、王権強化のポルトガル
六 東中欧─宗教改革の「先行性」と帝国的な「宗派化」のもとの寛容
七 南東欧バルカン地域─オスマン帝国統治下の寛容と「イスラーム化
八 ロシア─正教における帝権と教権、そして宗派化と帝国的な「寛容
第2章 近代─世俗的世界観の覇権の時代(一九世紀~二〇世紀前半)
一 フランス─「二つのフランスの争い」とライシテの確立
二 スペイン─「二つのスペインの争い」か、カトリックの優位か
三 イギリス─国教徒と非国教徒の作り出すダイナミズム
四 ドイツ─政教分離の論理とプロテスタント的なナショナル・アイデンティティ
五 南欧─「二つのイタリアの争い」、「二つのポルトガルの争い」
六 東中欧─帝国(のはざま)の政治的・宗教的アイデンティティ
七 南東欧バルカン地域─反西欧的な宗教的ナショナリズム
八 ロシア─宗教的ロシアに対する二つの評価とソヴィエト体制下の政教分離
第3章 現代─宗教的なものの回帰と再構成(二〇世紀後半以降)
一 スペイン─イスラームに寛容なカトリック的ライシテの国?
二 ドイツ─「キリスト教優遇型」の存続か変化か
三 イギリス─多様性の承認とブリティッシュネスの共有
四 フランス─ライシテの試練
五 南欧─カトリック優位の「宗教的多元主義」
六 東中欧─社会主義体制下の無神論から冷戦後のカトリック復興へ
七 南東欧バルカン地域─宗教とナショナリズムの結合と再活性化
八 ロシア─自由と管理の独特の編成
おわりに
第Ⅱ部 各論 世俗的ヨーロッパにおける宗教的なものの輪郭
〈政教関係の自明性を揺さぶる〉
第1章 一六、一七世紀スペインにおける政教関係─複合君主政と国家教会化(内村俊太)
はじめに
一 地域国家の政体
二 教会制度と国王教会保護権
三 複合君主政の下での国家教会化
おわりに
コラム:ポルトガルのカトリック教会と「独立」問題(西脇靖洋)
第2章 ポルトガルにおける権威主義体制の民主化とカトリック教会─リスボン総大司教アントニオ・リベイロの役割に注目して(西脇靖洋)
はじめに
一 権威主義体制の崩壊とカトリック教会
二 暫定期におけるカトリック教会
三 民主主義体制への移行とカトリック教会
おわりに
コラム:歴史を見る際の「補助線」としての理論的枠組み(内村俊太)
〈教育のなかの宗教を問う〉
第3章 ヨーロッパの公教育制度におけるイスラーム教育導入のプロセスと論点(見原礼子)
はじめに
一 ヨーロッパの公的教育機関における宗教
二 イスラーム教育導入のプロセスと論点
おわりに─ムスリムにとってのイスラーム教育の意味
コラム:世俗化社会における宗教教育と共生(増田一夫)
第4章 国家の世俗性のゆくえ─ロシアの宗教教育を事例として(井上まどか)
はじめに─ロシアにおける宗教復興と宗教教育
一 一九九〇年代の方向転換─宗教文化教育への道のり
二 「世俗性」原則をめぐって
おわりに
コラム:多民族国家における宗教教育(見原礼子)
〈宗教が対立と和解に関与するとき〉
第5章 冷戦下での西ドイツ・ポーランドの和解に宗教はどう関与したのか(木村護郎クリストフ・加藤久子)
はじめに
一 ドイツの側から─プロテスタント教会の『覚書』による世論の喚起と代替言説の提示
二 ポーランドの側から─カトリック司教団「声明」が残した葛藤と新たな自己理解
おわりに
コラム:「オトナになろう」と背中を押してくれる存在(立田由紀恵)
第6章 スレブレニツァのモスクと教会─内戦後のボスニアにおける宗教と社会(立田由紀恵)
はじめに─ボスニアにおける宗教、ナショナリズム、戦争
一 スレブレニツァとは─歴史と現状
二 スレブレニツァにおける宗教
三 スレブレニツァの宗教指導者による融和への道の模索
おわりに
コラム:スレブレニツァはヨーロッパの試験?(加藤久子)
〈宗教を信仰・実践・所属に分節化する〉
第7章 一九世紀イギリス文学の「世俗化」─エミリー・ブロンテの『嵐が丘』とスピリチュアリティ(小川公代)
はじめに
一 〈教会〉から離れても〈スピリチュアリティ〉はある
二 メソディズムの感受性文化─国教会と非国教会のあいだ
三 物質/身体と霊の融合
おわりに
コラム:霊性の彷徨はどこに向かうのか(木村護郎クリストフ)
第8章 聖母巡礼地における所属と実践─メジュゴリエの事例(岡本亮輔)
はじめに─「危険」な聖母出現
一 メジュゴリエを取り巻く三つの対立
二 ゴスパの政治的インパクト
三 所属から実践へ
おわりに
コラム:ヨーロッパ的現象としてのゴスパ出現(諸岡了介)
〈多様な生と(不)死の時代に〉
第9章 現代イギリスにおける宗教的多様性とホスピス(諸岡了介)
はじめに
一 問題の背景
二 宗教的多様性に応じた取り組み
三 チャプレン職の供給
四 ホスピスの文化的基盤
おわりに─将来の社会的課題
コラム:ホスピスケア、イギリスとロシアの共通点(井上まどか)
第10章 トランスヒューマニズムと「人新世」─科学技術時代の「信」のゆくえ(増田一夫)
はじめに─自己の身体とその境界
一 ディスラプションの時代
二 トランスヒューマニズムの宗教性
三 テクノロジーの形而上学vs自然の宗教
おわりに─超越としての人間
コラム:「トランスヒューマニズム」の系譜をロマン主義運動まで辿る(小川公代)
資料編
1.各国別宗教人口比と宗教人口比将来予想
2.礼拝出席率
3.政教関係
4.公立校における宗教教育
5.ヴェール禁止とニカブ・ブルカ禁止
6.人工妊娠中絶と同性婚の合法化
7.平均寿命と安楽死・医師幇助自殺