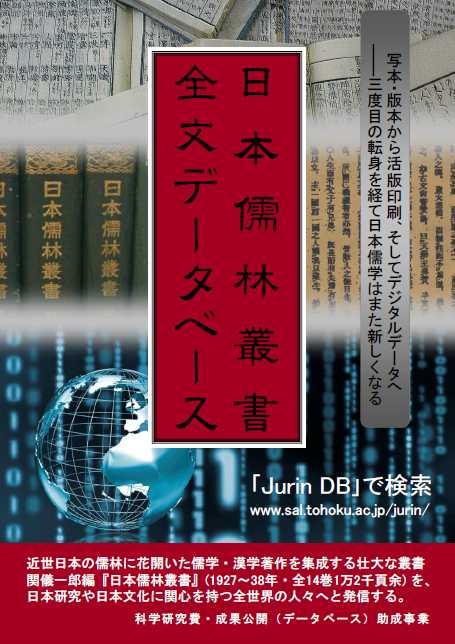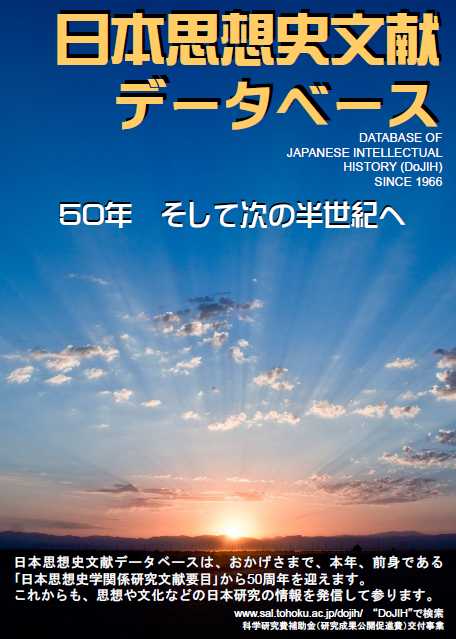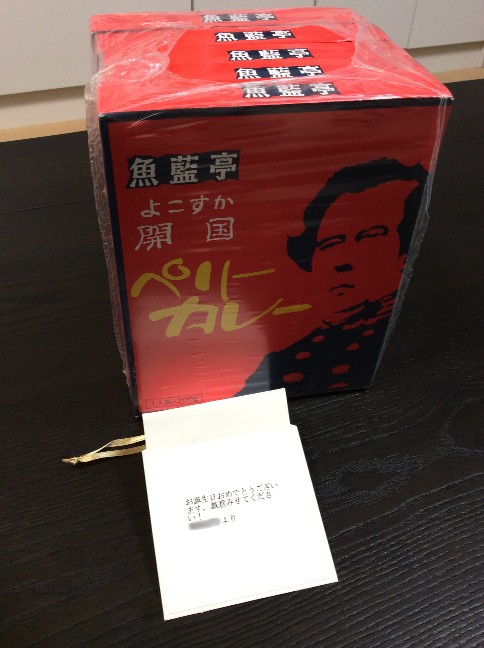今日のお題:『喪失とともに生きる:対話する死生学』(ポラーノ出版)
来月下旬に『喪失とともに生きる:対話する死生学』(ポラーノ出版)が刊行されるとのご案内を戴きましたのでお知らせいたします。
注文票を印刷してFAXでご注文いただければ幸い。
→注文票
『喪失とともに生きる:対話する死生学』
http://www.kyusenshoin.com/taiwasuru.html
 人生はあらゆる喪失に満ち、喪失とその悲哀とともに、どのように生きるかを問われている。これに対しグリーフ(悲嘆)ケアは、この心理的な危機にいかに対処するかという点に力点が置かれてきた。たしかに一時的な援助の手を差し伸べることは欠かせない。しかし私たちは、喪失が引き起こす当面の危機を乗り越えた後も、喪失を抱えて生きていかなければならない。
人生はあらゆる喪失に満ち、喪失とその悲哀とともに、どのように生きるかを問われている。これに対しグリーフ(悲嘆)ケアは、この心理的な危機にいかに対処するかという点に力点が置かれてきた。たしかに一時的な援助の手を差し伸べることは欠かせない。しかし私たちは、喪失が引き起こす当面の危機を乗り越えた後も、喪失を抱えて生きていかなければならない。
「あらゆる悲しみは、それを物語にするか、それについて物語を語ることで、耐えられるものになる」―本書では対話を通して、「喪失を抱えながら生きていく」意味を探っていく。
本書は七つの物語と各二つずつの対話から成り立っている。各物語は日常的に物語を聴き、物語とともに考える経験を重ねた対人援助職(グリーフカウンセラー、小児救急医、助産師、緩和ケア医、僧侶、看護師、NPO経営者)が物語る。それに対し、一つ目の対話で各物語の基本的な事柄や背景を、二つ目の対話では本文と異なった視点からの語り掛けを試みる。それぞれを哲学、宗教学、社会学、民俗学、仏教学等といった多様な専門家が応じることにより、物語がより視覚的・立体的に浮かび上がる。
関係者、そして喪失を抱えるすべての方へおくる。
序 対話する死生学 喪失とともに生きるために(竹之内裕文)
1章 喪失とともに生きる人たちとの出会い:グリーフカウンセリングの現場から(浅原聡子)
コメント1 日本におけるグリーフケアカウンセラー:臨床心理学と日本的心性の狭間で(浅見洋)
コメント2 グリーフサポートと民俗(井藤美由紀)
2章 こどものいのちを看取ること 小児救急の現場から(植田育也)
コメント1 寄り添いの変容 一世紀を経た二つの手記より(浅見洋)
コメント2 こどもを看取る家族への看護(阿川啓子)
3章 生を享けること、失うこと 周産期医療の現場から(増田智里)
コメント1 死産を経験した家族に対するサポート(河端久美子)
コメント2 幼い子を失った親の経験について(井藤美由紀)
4章 老病死に向き合う人から学ぶ 終末期ケアの現場から(奥野滋子)
コメント1 「自分を失うこと」とどう向き合うか(田代志門)
コメント2 「ホスピタル」はいかに「病院」となったか(桐原健真:160〜166頁)
5章 ホームを失って生きる 路上生活者の語りから(高瀬顕功)
コメント1 「ホーム」の意味について考える(浜渦辰二)
コメント2 困窮する人を「助ける」ということ:私たちの「居場所」をめぐって(松本曜一)
6章 がんが教えてくれたこと 患者・看護師としての体験から(佐藤仁和子)
コメント1 がん闘病者・サバイバーの喪失体験と生(草島悦子)
コメント2 病とともに生きるということ(高橋由貴)
7章 自他の喪失を支えるつながり グリーフから希望を(尾角光美)
コメント1 喪失から紡がれてゆくいのちのサポート(大河内大博)
コメント2 いのちの支え合いの場に立つ(中井弘和)
終章 死とともに生きることを学ぶ 対話する死生学のために(竹之内裕文)
編者
竹之内裕文(たけのうち ひろぶみ)
1967年生まれ。静岡大学農学部・創造科学技術大学院教授。東北大学大学院文学研究科博士課程修了、博士(文学)。専門は哲学、倫理学、死生学。主な著書に『どう生き、どう死ぬか―現場から考える死生学』(弓箭書院、2009年、共編著)、『七転び八起き寝たきりいのちの証―クチマウスで綴った筋ジス・自立生活20年』(新教出版社、2010年、編著)、『シリーズ生命倫理学・第4巻 終末期医療』(丸善出版、2012年、共著)ほか。
浅原聡子(あさはら さとこ)
1968年生まれ。GCC 認定グリーフカウンセラー、看護師、静岡大学非常勤講師。小児専門病院に20年間看護師として勤務した後、現在はカウンセリング、講演、セミナー等にて活動中。グリーフカウンセリングivy代表。
〒195-0061 東京都町田市鶴川2-11-4-301 ポラーノ出版
e-mail mail@polanopublishing.com
TEL 042-860-2075/FAX042-860-2029
web http://www.kyusenshoin.com
ご注文書 FAX 042-860-2029
注文票を印刷してFAXでご注文いただければ幸い。
→注文票
『喪失とともに生きる:対話する死生学』
http://www.kyusenshoin.com/taiwasuru.html
 人生はあらゆる喪失に満ち、喪失とその悲哀とともに、どのように生きるかを問われている。これに対しグリーフ(悲嘆)ケアは、この心理的な危機にいかに対処するかという点に力点が置かれてきた。たしかに一時的な援助の手を差し伸べることは欠かせない。しかし私たちは、喪失が引き起こす当面の危機を乗り越えた後も、喪失を抱えて生きていかなければならない。
人生はあらゆる喪失に満ち、喪失とその悲哀とともに、どのように生きるかを問われている。これに対しグリーフ(悲嘆)ケアは、この心理的な危機にいかに対処するかという点に力点が置かれてきた。たしかに一時的な援助の手を差し伸べることは欠かせない。しかし私たちは、喪失が引き起こす当面の危機を乗り越えた後も、喪失を抱えて生きていかなければならない。「あらゆる悲しみは、それを物語にするか、それについて物語を語ることで、耐えられるものになる」―本書では対話を通して、「喪失を抱えながら生きていく」意味を探っていく。
本書は七つの物語と各二つずつの対話から成り立っている。各物語は日常的に物語を聴き、物語とともに考える経験を重ねた対人援助職(グリーフカウンセラー、小児救急医、助産師、緩和ケア医、僧侶、看護師、NPO経営者)が物語る。それに対し、一つ目の対話で各物語の基本的な事柄や背景を、二つ目の対話では本文と異なった視点からの語り掛けを試みる。それぞれを哲学、宗教学、社会学、民俗学、仏教学等といった多様な専門家が応じることにより、物語がより視覚的・立体的に浮かび上がる。
関係者、そして喪失を抱えるすべての方へおくる。
序 対話する死生学 喪失とともに生きるために(竹之内裕文)
1章 喪失とともに生きる人たちとの出会い:グリーフカウンセリングの現場から(浅原聡子)
コメント1 日本におけるグリーフケアカウンセラー:臨床心理学と日本的心性の狭間で(浅見洋)
コメント2 グリーフサポートと民俗(井藤美由紀)
2章 こどものいのちを看取ること 小児救急の現場から(植田育也)
コメント1 寄り添いの変容 一世紀を経た二つの手記より(浅見洋)
コメント2 こどもを看取る家族への看護(阿川啓子)
3章 生を享けること、失うこと 周産期医療の現場から(増田智里)
コメント1 死産を経験した家族に対するサポート(河端久美子)
コメント2 幼い子を失った親の経験について(井藤美由紀)
4章 老病死に向き合う人から学ぶ 終末期ケアの現場から(奥野滋子)
コメント1 「自分を失うこと」とどう向き合うか(田代志門)
コメント2 「ホスピタル」はいかに「病院」となったか(桐原健真:160〜166頁)
5章 ホームを失って生きる 路上生活者の語りから(高瀬顕功)
コメント1 「ホーム」の意味について考える(浜渦辰二)
コメント2 困窮する人を「助ける」ということ:私たちの「居場所」をめぐって(松本曜一)
6章 がんが教えてくれたこと 患者・看護師としての体験から(佐藤仁和子)
コメント1 がん闘病者・サバイバーの喪失体験と生(草島悦子)
コメント2 病とともに生きるということ(高橋由貴)
7章 自他の喪失を支えるつながり グリーフから希望を(尾角光美)
コメント1 喪失から紡がれてゆくいのちのサポート(大河内大博)
コメント2 いのちの支え合いの場に立つ(中井弘和)
終章 死とともに生きることを学ぶ 対話する死生学のために(竹之内裕文)
編者
竹之内裕文(たけのうち ひろぶみ)
1967年生まれ。静岡大学農学部・創造科学技術大学院教授。東北大学大学院文学研究科博士課程修了、博士(文学)。専門は哲学、倫理学、死生学。主な著書に『どう生き、どう死ぬか―現場から考える死生学』(弓箭書院、2009年、共編著)、『七転び八起き寝たきりいのちの証―クチマウスで綴った筋ジス・自立生活20年』(新教出版社、2010年、編著)、『シリーズ生命倫理学・第4巻 終末期医療』(丸善出版、2012年、共著)ほか。
浅原聡子(あさはら さとこ)
1968年生まれ。GCC 認定グリーフカウンセラー、看護師、静岡大学非常勤講師。小児専門病院に20年間看護師として勤務した後、現在はカウンセリング、講演、セミナー等にて活動中。グリーフカウンセリングivy代表。
〒195-0061 東京都町田市鶴川2-11-4-301 ポラーノ出版
e-mail mail@polanopublishing.com
TEL 042-860-2075/FAX042-860-2029
web http://www.kyusenshoin.com
ご注文書 FAX 042-860-2029